●鎌倉中期にできた「続後撰集」20巻。承久の乱以降、衰退してしまった内裏歌壇復活への後嵯峨院の強い意向があった第10番目の勅撰和歌集。
●資料提供のために嵯峨院が「宝治百首」という大規模な催しを行っていますが、歌学・歌道で朝廷に仕えた御子左家(83番・藤原俊成、97番・定家ら)と、それに対抗する歌風がせめぎ合った歌集です。
●入集の多い歌は、97番・藤原定家(43首)、西園寺実氏(34首)、91番・藤原良経(29首)、83番・藤原俊成(28首)です。
●為家は父である定家が撰進した「新勅撰集」を「古今集」に見立てて、それを継承する歌を集めました。
●鎌倉幕府に遠慮して「新勅撰集」では避けた99番・後鳥羽院(29首)、土御門院(26首)、100番・順徳院(17首)の歌を多く入集させています。
●各巻とも歌を効果的に配置した調和のとれた構成です。
●「新勅撰集」に比べて明るく華やかな雰囲気であるのは、内裏歌壇が復活したからかもしれません。
●ただし、雑歌中の述懐歌には、苦い人生観を率直に述べた痛切な歌が並んでいます。 |
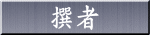

藤原為家 |